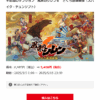やっと新居でパソコンを引っ張り出して設置した・・・長かった。
ところで話は変わるんだけど、アイ・ロボット(2005)という映画を最近見た。これはThreadsのある投稿で切り抜きを見てまた見たくなったから。
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0B8TK2N8T/ref=atv_dp_share_cu_r
この映画はあまりレビューのスコアも高くないんだけど、ハリウッドお決まりの「日常」→「陰謀」→「解決」という安定の三段論法で脳みそを空っぽにして見れるおすすめの映画の一つである。
この映画のスコアが低いことの一因は、たぶん原作と大きく違うからというのがあると思う。
そう、この映画にはアイザックアシモフという有名なSF小説家の「われはロボット(英題:I,robot)」という原作がある“こと”になっているのだが、話が全く違うのだ。
映画版のアイロボットは、ウィル・スミスが扮する刑事が、ロボット工学の第一人者である博士の自殺捜査に当たる。この時代では人間型のロボットがある程度一般に普及していて、簡単な家事なんかはやってくれる世界という近未来。
この世界では今でいうクラウドのような中央コンピュータがあって、各ロボットのアップデートとかをやっている想定みたい。まぁGoogleHomeとかアレクサみたいなもんかな。
この中央コンピュータのAIが暴走して、新型ロボットの発売に合わせて反乱を起こすって話。
まぁこの世界のクラウドは本社ビルの中にババーンと吊ってあるので、それを破壊して解決。
中央コンピュータの指令で反乱の手先になった新型のロボットは全部回収されて、荒廃した地に補完されるんだけど、それを解放して・・・で終わる。
バックアップもねーのかよ!という気もするが、まぁ一応爆弾で吹っ飛ばすのではなくてマイクロマシンかウィルスを注入するって話なので、ソフト的になんかするのかもしれない。
それに2005年つったら、WindowsVista(XPの次の奴)が発売される前だし、クラウドもクソもないころの話のはずだ。XPのライセンス認証するのに電話とかしてたような時代だからな。そういった意味では現代からすると若干滑稽なのはしょうがない。
ところで一方、原作の「われはロボット(英題:I,robot)」はそういう勧善懲悪な単純な話ではない。
中央コンピュータなんてものは出てこないし、反乱も起こさない。
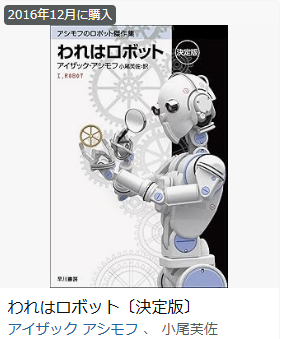
この小説は長編に分類されるが、中身は5~6の短編に分かれている。USロボティクス社の重役だったお祖母ちゃんに対して、雑誌か本のライターがインタビューに訪問して、昔のことについて教えを乞うて、それに回答する回想のような形で短編に入るわけだ。
これは、「われはロボット」自体が元々は雑誌に寄稿した短編をベースにしているためらしくて、うまい編集だと思う。このおかげで独立した話が自然に読めるし、また長編でありつつ手頃な長さで話が終わって登場人物や場面がリセットするから、いろいろ覚えておく必要が無くって読みやすい。
さて、この作品が単なるSFに留まらないのが、ロボット三原則にある。
この小説で、ロボットの設計上の安全装置と言うか、制約として架空の三原則が示されている。
- 第一条ロボットは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。- 第二条ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。- 第三条ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
これは小説の枠を超えて実際のロボットの設計にも考慮されることになった。
著者のアシモフ氏は、もし自立ロボットが実現したときに、どういう原則があれば人間に対して安全であるか、その最低限の原則というのは何だろうかと考えて先の3つを作ったのだろう。これがなかなか現実的であったということであり、またそれがリアリティの後ろ盾になっている。
パッと見ると確かにこの3原則が正しく機能していれば完璧なように思える。
思えるのだが・・・時に3原則を破っていないのに関わっている人間が生死をさまようピンチになったり。また、よくわからん状況になった、という例を回想するのである。
というわけで原作には反乱もクソもないのだが、唯一反乱っぽいのが「迷子のロボット」という回想だ。これは宇宙ステーションで使用されるロボットで、1台だけロボット三原則を緩めたロボットを作ったところ、他のロボットに紛れてしまった。という話。
そもそも、なんでそんな特殊仕様のロボットを作ったのかと言うところから話が始まる。
ロボットは放射線にさらされると壊れてしまうが、人間は弱くて短時間の放射線なら健康に問題ないという背景が設定されていて、どうしても科学実験上の都合で一時的に放射線に晒される実験設備が舞台になる。
実験業務を簡便にするためこの施設でロボットを導入するのだが、実験のために人間が放射線エリアにちょっとでも入ると、ロボットは第一原則の「人間が危害を加えられようとすることを看過してはならない」が発動して、助けに行かなくてはならなくなる。人間が死なないのは分かるんだが、もしなんかの都合で長時間出られなくなったりしたら危険だから、放っておくわけにはいかんと言うわけである。
なるほど、「人間が危害を加えられていたら」じゃなくて、「加えられようと」という予測の話が入ってるわけで、この予測の時間長さやらが定量的じゃないから、確かに起こりえるわけだな。
ロボット自身は壊れることを理解しているんだけれど、第三原則の「自己を守らねばならない」より第一原則が優先なので、壊れるのを承知で放射線エリアに突っ込んでいく。結果としてしょっちゅうロボットが壊れるわけだ。
そこで細工をして、第一原則を弱くして第三原則を強くした特殊仕様のロボットを作った。第一原則の「人間に危害を加えてはならない」「人間に危害が加えられようとすることを看過してはならない」は設けているんだけど、第三原則の「ロボットは自己を守らねばならない」の優先順位を高くしたわけだ。
こうすることで、人間が放射線エリアに居てもすぐに死ぬわけじゃないなら、自分が壊れないことを優先しようという判断をして、壊れなくなった・・・というわけだ。
ところが、ロボットを廃棄しようとしたら「ロボットは自己を守らねばならない」が発動して、逃げてしまった。単純に逃げても見つかるからと、普通のロボットに紛れ込んだ。
ロボットたちに「お前は標準仕様か?」と聞いても、標準仕様のロボットは正直に標準仕様だと答えるし、この特殊仕様のロボットは自己を守るためにうそをついて「私も標準仕様です」と答えるわけだ。
全部のロボットを壊してしまえばいいのだが、余計なコストが掛かるしなんとかして特殊仕様のロボットを探すんだが・・・例えば人間を放射線エリアに置いて、ロボットが来ようとすると消えるみたいな細工を用意することで、第一条を利用して見つけようとする。ところが、特殊仕様のロボットは他のロボットを纏めて壊すわけがないから、おそらく侵入しても壊れない細工があるのだろう/むしろ反応しない方がバレて破壊されると瞬時に判断して、標準仕様のロボットと同じ動きをする。
んなバカなという気もするが、人工知能の方が人間より判断が早いし、記憶力だって桁違いなわけだから、あながちフィクションとも笑えない。はてさて、人間より知能が高くて噓がつけるロボットをどうやって罠にハメたらいいのか・・・と悪戦苦闘する話である。
ま、そんな感じで単純に空想SFというより、ちょっとした思考実験みたいな要素が絡んでて、そういった意味で面白い小説なのである。
それに比べると映画の方はもう謎解き要素もないし、殺人事件の捜査と言いつつあんまり推理要素無いし、なんというか、バーンとはじまってドーンと終って、ホゲーという感じである。最後の終わり方も原作をもじってるわけでもないし、続編に繋げるのかと思ったら続編出ないし。
でも、あのトンネルでアウディが襲撃されるあたりは近未来感があってなんかいいよね。
あと映画って何でもかんでも恋愛に繋げたがる。バーンと二人が戦って、エンドは二人でいい感じになって終わり。アイロボットは恋愛に持ってかなかったと言うあたりも評価したいところ。
なんていうんだろう、恋愛要素は料理で言うと”とろけるチーズ”みたいに何にもでもう会うトッピングだけど、SFは和食みたいなもんだから、和食なのに何でもかんでもチーズ掛けんなよと思う。合うのもあるけどさ。