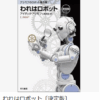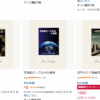なんで今更・・・
なんか最近アマプラでプライム課金だけで見れる面白い作品が無くなって来て・・・なんとなく、もう一回見てみたバックトゥザフューチャ。
何回も見てるし、筋書きも覚えているから、まぁBGM程度に見よう。キリが良いところで中断しても良いしなーと思って見始めたんだけど、めっちゃ面白い。
なんだかんだで、アマプラに無い3までDVD借りてきて見てしまった。
なんでだろうなぁ。筋書きとか覚えているし、すごいグラフィックがあるわけでもないのだが、面白くて見入ってしまう。テンポが良いのだろうか?凄く満足だったのだが、何が満足だったのかよく分からないのである。
ま、考えるのも楽しいけれど、探してみたらちゃんと考察している人が居た。
上の記事のチャートを見るとなんとなく、面白かった要因が分かった気がする。
2つのストーリーが自然に同時進行している
メインパートである過去編のところで2つの話が同時に起こってることが、テンポよく飽きが来ないポイントの一つだと思う。
話の一つはタイムマシーンを動くようにして、現代に戻ることって言う大筋。
そこにもう一個の話である、親父とお袋の出会いを邪魔しちゃった問題を解決するために、仲立ちをするって話を絡めている。
ただ単に『うっかり過去に行っちゃって現代に戻ってこれない』っていうだけでも面白いんだろうけど、この親父とお袋をなんとかするっていうドタバタ劇が入っているおかげで、間延び感が無いんだろうなぁ。
全く関係ない話を二つ並行したら面白くなるわけじゃなくて、タイムマシーンが核燃料の代わりに唯一分かっている落雷を使うっていう制約による時間制限が、この2つの関係ない話を連結しているんだよね。
仮にタイムマシーンがある程度自由に動くなら、別の解決策も出来ちゃう。
また、仮に一回動かしたら終わりだったとしても、タイミングの縛りが無いのであれば、タイムスリップと仲立ち作戦を同時に行う必然性が無い。まず、仲立ちをうまく済ませて、落ち着いてタイムスリップの準備に入ればいい。
ドラマとかだったらそういう構成になるはず。でも1本の映画の中でバタバタ面白くやるには、誰もが納得する形で同時進行の方が面白い。
伏線の張り方がうまい
落雷で思い出したけど、伏線の張り方なんかも凄く面白くて数が多いんじゃないかと思う。
最初にさりげなく出てきた背景的な裁判所の時計→落雷壊れているが歴史的なものだから保存したいというビラを貰う→ビラに連絡先を書いてもらって持ってる→過去で莫大な電気が必要だが・・・という繋げ方とかすごい。
落雷を使うってアイディアは良いとして、それをうまく補足するっていうのを観客に納得させるためには、日時とか漠然とした位置が分かる程度じゃダメ。
例えば『落雷で焼けた木』とか、『落雷で壊れた建物』じゃあだめだ。当時の日付は残っててもおかしくないけど、時刻まで残ってるのはおかしい。
”落雷で壊れた歴史的な時計”という設定にすることで、秒単位で落雷の時間が分かっていても納得できる。
雑なご都合主義で、今か今かと待ってて偶然落雷があたってヨカッタ!じゃなく、こういう一定の論理性があることで納得できる。
雷が電線をバシバシっと走っていくとか、それタイムマシーンに入力できる電圧なのか?十分なエネルギー量が本当にあるのか?などと言った、細かいご都合主義を覆い隠して、「なるほど!」と思わせてくれる。
その他にもいろんなところが伏線になってるんだよなぁ。
しょっぱなの現代で、ビフが親父の頭を小突いて言うこと効かせようとする独特の仕草・・・たまにあるちょっとクドい悪役の表現で、これ一発きりならやや不愉快なだけ。だけど、そのすぐ後になる過去パートで、青年時代のビフが親父に対して全く同じことをやるので、「こいつ昔からそれやってんのか!変わってねーな!」と笑いに換えてくれるし、何の説明も無くてもこいつは間違いなくビフの若いころだと分からせてくれる。
他にタイムマシーンで面白い話あったっけ?
そういえば、タイムマシーン物と言えば-0だな・・・広瀬正というSFでは有名な作家の代表小説。
いや、単に過去に行って戻っただけでは面白くないだろう?例えば・・・と、思って真っ先に思い浮かんだタイムマシーン物と言えば-0なのよ。
これはこれで凄い名作でね。1970年に書かれた小説で、その時代に太平洋戦争時代にタイムマシーンがあって、それのせいで開戦前にタイムスリップしたら・・・という話なので、昔の人の昔が凄いリアルに描かれていて面白い。見知ったもの、銀座や世田谷が当時はどうだったのかなんかが凄くリアルだ。
これはこれで話が長くなるから置いとくか・・・
でも、そういえば±0も単に過去に行って戻ってくるって話じゃなかったな。
いや、違うな。ある意味戻ってこれないんだったなそういや。
タイムマシーンで戻れたのって夏への扉くらいか?
この辺のタイムトラベルものって、作者どおしアイディアを利用しているんじゃないかと思うんだけど、発行の位置関係ってどうなるんだろう?
1956:夏への扉[ロバート・ハイライン著]
1970:マイナス・ゼロ[広瀬 正著]
1985:バックトゥザフューチャー[スティーブン・スピルバーグ]
調べたら結構バラバラだった。
どういう関連性になってるんだろうなぁ・・・もう一回読んでみるか。
ちなみにアイキャッチは「バックトゥザフューチャー風のイラストを描いて」とCopilotに相談したところ、「著作権の都合で書けません。雰囲気だけを取り入れたオリジナルの画像なら書けます」というので、「もう雰囲気だけで全然違うの書いて」と頼んで出てきたものだけど・・・これ本家から怒られねーだろうな・・・だいぶ寄ってる気がするんだけど。